院長からのご挨拶
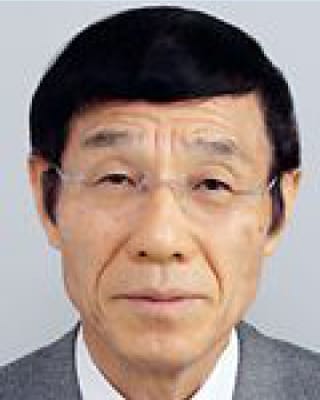 武市クリニック 院長
医学博士
内分泌甲状腺外科専門医
武市クリニック 院長
医学博士
内分泌甲状腺外科専門医【私の考えるヒトにとって大切な事は】、働ける・動ける力を維持しながらの加齢だと思っていまして、「年齢と共に低下する甲状腺ホルモンを補充し、体を動かし、働きながら100歳まで、そして110歳まで生きていくこと」。これを私は“甲状腺健康寿命”(の延長)と表現しています。 もう一つ、今の時代に最も大切なことは、青壮年期の出産数を増やすことです。そのためには甲状腺ホルモンの異常で起こる生理不順を治し、青年期と、壮年期の早め、に第一子をもうけて頂き、思春期・青年期には甲状腺具常で起こる精神的異常を鑑別し、不必要な長期の“精神安定剤や睡眠薬の使用”をできるだけ控えて、生理不順に注意して頂くよう勧めています。安定剤、睡眠薬を若くから長期使用しているからと言って、妊娠を諦めて頂かないためです。 このような甲状腺と加齢そして他臓器との関係を知ると、「ヒトの健康と妊娠・出産、アンチエイジング、健康寿命の延長に関して、“甲状腺の諸臓器に対する守備範囲の広さ」が理解して頂けるものと思います。 (附-1)甲状腺の腫瘤(できもの)に気付かれた時、大事な事はまず癌か否かを穿刺吸引細胞診(穿刺診)で診断しますが、1.0cm以下だと殆どは手術せず経過観察をします。それ以上は手術になるものを穿刺診と共に超音波エコーでの周囲浸潤状況を確認します。 良性の腫瘤は「甲状線に何かありますよ」というサインだと思って頂く事が大切です。甲状護機能、年齢、症状を診て対処します。甲状腺の癌は殆どが経通の良いものですが、中には未分化癌のように命にかかわるものがあり、早期の穿刺診が重要です。 (附-2)「老化は首から始まる」に関しましては、次回の武市(甲状線)クリニックのホームページで説明したいと思います。
令和7年1月・記 武市クリニック(甲状腺)
広島大学で
広島大学で1965年から1995年まで甲状腺研修と診療を続けていました。その間、甲状腺の外科・内科を学びながら、途中で原医研放射線誘発癌部門では放射線発癌と病理を、放射線医学総合研究所と米国ロサンゼルスのULCAとワズワース退役軍人病院では“放射線免疫”と“加齢免疫”を学び、その中でヒトの寿命は遺伝子で110歳とされている事を知りました。 帰国して免疫以上に甲状腺ホルモンが加齢に関与しているのではと気付き、”加齢甲状腺”と呼んでの診療も続けていました。 所属教室では甲状腺・副甲状腺・唾液腺・乳腺と共に肝・腎移殖や血管外科、副腎、消化器(胃・腸)外科等の他臓器の患者さんを診ることができたため、甲状腺とこれら他臓器との関係を学ぶ事ができました。 また、広島の検診所からの依頼で、広島大学での最初の10~20年は原爆被爆者の検診のお手伝いもしていました。診療を続ける中で甲状腺癌と甲状腺内科診療の患者さんには多くの原爆被爆者の方がおられ、その患者さんが自分の子供、孫に放射線異常が遺伝しないかを心配される方も多く、気が付けば50を超える家族の甲状腺を診ていました。
現在行っている武市クリニックでの甲状腺診療
(原爆被爆者の経験も踏まえて)
武市甲状腺クリニックで
武市甲状腺クリニックは1995年11月に開院しました。これまでに3万人近くの患者さんが来院され、2,000人を超える人が原爆被爆者でした。その中に甲状腺家族が含まれていまして、これらの甲状腺診療経験から「甲状腺疾患診断フロー(主に甲状腺腫・甲状腺機能状態から一内科系を中心に一)」【社)広島市医師会臨床検査センター疾患プロファイル構築委員会・甲状腺担当・武市宜雄(2001.1.1)】を21世紀初頭に発刊できました。 上記委員会の協力で発刊できましたこの表は、多くの患者さんから得られた自覚症状と検診検査データを解析し、これを年齢別に若者から老人への8段階の年齢別に分け、さらに甲状腺機能を大きく亢進症と低下症に分けた上で、甲状腺の診断名を記入した”年齢別甲状腺疾患診断法のフローチャート”と言えるものでした。 これを可能にしたものは、甲状腺関係の自己抗体(TRAb、TgAb、TPOAb)を含めた色々の血液検査と共に、甲状腺腫の血流、血流量、硬さ等を調べる事ができる相音波カラーエコー診断装置の進歩により、より高感度な検査結果が得られるようになったからであります。今でもこのフローチャートを手許に置いて甲状腺診療を描けています。
甲状腺疾患診断フロー「年齢別甲状腺疾患診断法」のフローチャートの特徴
この「診断フロー」での甲状腺の特徴を簡単に示しますと、 ①乳幼児期はクレチン病 ②小児期は急性化膿性甲状腺炎と生理 ③思春期は女児の生理と思春期甲状腺腫そしてバセドウ病初期 ④青年期はバセドウ病と妊娠・出産後の機能異常 ⑤壮年期は私の言う”バセドウ橋本混在型(同時性と具時性あり)甲状腺腫” ⑥更年期は甲状腺機能低下を伴う橋本病と更年期障害 ⑦準老年期は機能低下症著明な橋本病 ⑧老年期は甲状腺萎縮を伴う甲状腺機能低下症 の診断がベースとなっています。 全体として女性特有の症状、疾患と深くかかわっています。
甲状腺ホルモンの働き
甲状腺ホルモン機能の亢進症(特に若い頃)と低下症(特に年をとって)の診断で大事なポイントは、 ①精神面での躁・パニックとうつ ②動悸と疲労感そして不機脈 ③頻脈と徐脈 ④微熱と寒がり ⑤多汗と皮膚乾燥 ⑥消化器異常として下痢と便秘、胃潰瘍と逆流性食道炎や体重異常(やせと肥満)、そして肝機能異常 ⑦生理不順と不妊 ⑧流・早産 ⑨高血圧 これに加えて ⑩バセドウ病では特に眼球突出と心房細動、ふくらはぎの痙攣 ⑪橋本病では高脂血症とこれに伴う脳梗塞、糖尿病と肝、腎機能障害、そして加齢に伴う筋力・精力の低下や・更年期症状、健忘症、認知症等です。
まとめ
まとめますと、甲状腺ホルモンの影響は
A:年齢別には
①思春期までは特に体と知能の発育に重要で ②思春期・青年期には学業への一時的な影響と、躁とパニック ③青壮年期には仕事と子作りとパニック、加えて三大代謝病(糖尿病、高脂血症、高尿酸血症) ④更年期には閉経とうつ ⑤準老年期には体力低下(筋力・精力低下) そして ⑥老年期の認知症です。
B:加えて、加齢に影響する特徴として
①慢性甲状腺炎は自己免疫疾患・膠原病の仲間であり、リウマチ性関節炎もこの中に含まれており、共に、加齢とともに進行する傾向があります。そのため慢性甲状腺炎に伴う甲状腺機能低下症に対しては準老年期からは体力を温存しての“アンチエイジングと健康寿命の延長”に心がけ、加えて体を動かしての心のバランスが不可欠となります。 ②甲状験ホルモン異常は特に女性に多く、各年齢層で色々な症状とかかわります。それを注意して治療することとなります。
医師のプロフィール・クリニック内の様子
院長略歴
- 昭和43年3月
- 広島大学医学部医学科卒業
- 昭和43年4月〜
- 広島大学医学部附属病院研修医
- 昭和44年10月
- 大阪市湯川胃腸病院勤務
- 昭和45年4月〜
- 広島大学原爆放射能医学研究所(外科)診療研修医員
- 昭和46年4月〜
- 同上 医員
- 昭和48年6月〜
- 広島大学原爆放射能医学研究所(放射線誘発癌研究部門・病理)助手
- 昭和52年6月〜53年9月
- アメリカUCLA助手(Research Associate)
- 昭和53年10月〜昭和55年3月
- 放射線影響研究所病理部来所研究員
- 昭和54年4月〜
- 広島大学医学部附属病院・第二外科:医員
- 昭和56年11月〜
- 同上:助手
- 昭和59年3月〜
- 同上:講師併任
- 昭和63年2月〜平成7年10月
- 同上:講師
- 平成7年11月〜現在に至る
- 武市(甲状腺)クリニック院長
- 平成11年7月〜平成14年3月
- 広島大学非常勤講師(原爆放射能医学研究所:疫学・社会医学研究分野)
- 平成14年4月〜平成17年3月
- (同上:放射線システム医学研究部門)
- 平成17年4月〜平成18年3月
- (同上:附属国際放射線情報センター)
- 平成18年4月〜平成22年3月
- (同上:放射線システム医学研究部門)
- 平成22年4月〜平成23年3月
- (同上:放射線影響評価研究部門)
- 平成23年4月〜平成29年3月
- (同上:教養教育本部)
- 平成24年10月〜令和2年9月
- 島根大学医学部臨床教授
- 平成29年4月〜現在に至る
- 広島大学客員講師(教育本部全学教育統括部)
- 平成29年4月〜令和元年3月
- 広島大学客員教授(大学院医歯薬保健学研究科)
- 令和元年4月〜現在に至る
- 広島大学客員教授(大学院医系科学研究科)
- 令和6年8月
- 外務大臣賞受賞
資格
- 昭和51年7月22日
- 医学博士
- 昭和63年〜平成20年
- 日本内分泌外科学会評議員
- 平成2年〜
- 日本消化器外科学会認定医
- 平成2年〜
- 日本外科学会認定医
- 平成9年〜令和3年
- 日本臨床外科学会評議員
- 平成21年〜令和6年
- 日本内分泌甲状腺外科專門医
- 平成22年〜
- 日本生涯教育認定医
- 平成27年〜
- 日本外科学会専門医
- 令和2年〜令和6年
- 内分泌外科指導医
- 令和4年〜
- 日本臨床外科学会特別会員
- 令和7年〜
- 内分泌外科登録認定医
所属学会
日本外科学会・日本臨床外科学会・日本病理学会・日本癌学会・日本甲状腺学会・日本甲状腺外科学会・日本内分泌学会・日本内分泌外科学会・日本放射線影響学会・日本臨床細胞診学会(広島県支部)・日本消化器外科学会
專門
内分泌(甲状腺)外科・甲状腺・放射線発癌
著書
- 外科基本手術シリーズ5「甲状腺の手術」(へるす出版刊)昭和58年6月発行
- 内分泌外科 標準手術アトラス(インターメルク刊)平成4年1月発行
- 「放射線被曝と甲状腺がん ー広島、チェルノブイリ、セミパラチンスクー」(溪水社刊)平成23年8月発行 他
クリニック内の様子
スタッフ
看護師 8名 / 臨床検査技師 5名 / 受付事務 8名
甲状腺に関係した各種メンタル症状の診察について
院長より診察のご紹介
甲状腺の関係では機能亢進症で躁(ソウ)、機能低下症でウツがみられることが多いものです。加齢と共に甲状腺機能も低下し、健忘症・認知症の症状も増加します。更に更年期症状として、あるいは青年期の妊娠・出産に伴って甲状腺機能異常が起こることも多く、これに精神症状を伴ってくることもあります。こういった甲状腺に関係した幅広いメンタルな症状を診て頂くこととなります。 現在のような長寿社会では不眠症も現代病の1つになってきており、この不眠症が認知症を増悪させる要因ともなります。この不眠症も甲状腺専門の武市院長と共に診て頂きます。井上先生は上記の認知症と共に、不安症(パニック)も専門とされています。 井上先生はセミパラチンスク(旧ソ連の核実験場)に何度も行かれ、セミパラチンスク医科大学では放射線被爆者の精神症状の講義も続けておられますので、原爆被爆者の方の精神症状、加齢に伴う精神症状も診て頂けると思います。
井上 顕 先生からのご挨拶
「うつかもしれない」と思い浮かぶことが大切!
 高知大学教育研究部医療学系臨床医学部門保健管理センター 教授
医学博士
高知大学教育研究部医療学系臨床医学部門保健管理センター 教授
医学博士
4月から武市クリニックにて月2回診療いたします高知大学の井上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。「精神医学、精神保健を中心とした公衆衛生学」を専門にしております。武市院長先生が長年にわたりカザフスタンのセミパラチンスク核実験場周辺住民に対する検診や講演活動をなされている中で、2013年より私も先生のグループの仲間に入れていただいています。 武市院長先生は身体疾患と精神症状の合併に関して両分野の専門的な対応の必要性を強く考慮されておられます。私も先生と同様の考えです。その第一歩が「うつかもしれない」という気づきを皆さんにしていただくことで、併存する他の疾患の発見にもつながり得るのだと思っています。下記にその側面からの3項目を記載してみました。何らかのご参考になりましたら幸いです。
診療において私が心がけていることは恩師の1人である貝谷久宣先生(現 医療法人和楽会理事長:パニック症・社交不安症を中心とした不安症やうつ病の専門医療機関)に教えを受けた「痛みをとる」ということです。身体の痛みという言葉があるように、こころの疾患にも痛みがあり、それは苦痛を意味します。 各々の現状と必要事項を理解することはもちろん、最善の治療と対応にて苦痛を少しずつでも取り除き、安心した生活を送れる一役となればと考えております。ぜひともお気軽にご相談いただけたらと思います。
「うつ」と「甲状腺機能障害」
甲状腺機能亢進症
主な精神症状は気分の変動です。強い不安やイライラ感を認めたり、躁状態・時にはうつ状態などを呈することがあります。
甲状腺機能低下症
精神症状においてうつ状態を認めることがあります。すなわち、うつ状態と甲状腺機能障害とは同時に治療をせねばならないこととあるわけです。広義に解釈すると、亢進症ではうつ状態ばかりでなく躁状態や不安等への対応が必要になる状況もあり得ます。身体科医と精神科医各々が甲状腺と精神症状の両対応をすることもありますが、専門性を考えると身体科医と精神科医が協同してこの治療にあたることが安心です。先述しましたように武市院長先生はその視点の重要性を以前から示唆されており、このたび武市クリニックにてその実施となる一助になれればと思っている次第です。
「うつ」と「認知症」
認知症は「アルツハイマー病による認知症」、「血管性認知症」、「レビー小体病を伴う認知症」、「前頭側頭型認知症」、「他事項による認知症」が挙がります。ここで「アルツハイマー病による認知症」と「血管性認知症」を取り上げてみますと、「アルツハイマー病による認知症」の方の約2割に軽度のうつ状態が存在すると言われています。また、「血管性認知症」は「アルツハイマー病による認知症」と比べてうつ状態の存在が高率であると示唆されています。「レビー小体病を伴う認知症」などもうつ状態を認めることがあります。 うつかもしれないと思うことで認知症の発見につながる可能性もあるのです。
「うつ」と「不安症」
不安症群には「分離不安症」・「パニック症」・「社交不安症」・「全般不安症」などが含まれています。 最近話題になっている「パニック症」をここでは述べてみます。「パニック症」は強い不安と様々な症状を伴うパニック発作(パニック発作)を繰り返し体験することで、再び発作が生じることを過度に心配(予期不安)し、また、発作の際に逃げられないような場所や状況を回避(広場恐怖)しようとする疾患です。「パニック発作」の生涯発生率は約10%、「パニック症」の生涯有病率は3%前後と言われています。「パニック症」における約3〜6割はうつ病や躁うつ病等を合併するとの示唆がありますし、不安症の何かの疾患をもつ患者さんにおけるうつ病の生涯有病率は約4割と示している報告も認めます。 したがって、うつかもしれないと思い浮かぶことでパニック症を含む不安症を気づくことにもなり得ます。
医師のプロフィール
院長略歴
現 高知大学教育研究部医療学系 臨床医学部門保健管理センター 教授・医学博士
その他
- 高知大学国際連携推進センター国際プロジェクト部門長
- 高知大学学生総合支援センター
- 高知大学 朝倉・小津・物部キャンパス産業医(精神担当)
- セメイ国立医科大学名誉教授(カザフスタン)
- 藤田医科大学医学部客員教授
- 群馬大学医学部非常勤講師
- 島根大学医学部嘱託講師



